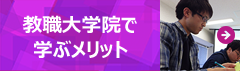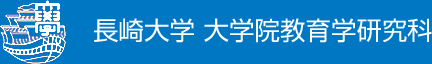教員としての自信がつく

人脈は宝物

3年間で1つ免許が取得できるプログラム

教科指導力の向上

教員採用試験(出願予定の都道府県・政令都市の募集要項で必ず確認して下さい)

教職大学院に進学を予定者、または教職大学院に在籍者が、長崎県の実施する教員採用選考試験に合格した場合、申請により、採用候補者の名簿登載期間を延長できる制度があります。
奨学金の返還免除制度による経済支援の充実化
研究奨励金
在学生・修了生からのメッセージ
増本 渚 先生
(子ども理解・特別支援教育実践コース[2年プログラム]令和5年度修了生、現 公立小学校教員)
自分の強みを築くために
教師として経験を積み上げていくことで、少しずつ教師としての軸をもち、自分の言動や行動に自信をもつことができるようになりました。しかし、虐待や孤立など子どもたちの教育的ニーズが複雑で多様となり、今まで培ってきた経験を生かすことができず、自信のないまま援助する経験が増え、自分の教師としての力量のなさを痛感するようになりました。それと同時に「子ども達を上手く援助することができるようになりたい」「子ども一人ひとりの思いやSOSを受け止めることができるようになりたい」という強い思いをもつようになり、子ども理解・特別支援教育実践コースで学ぶことを決意しました。
大学院では、学校心理学の心理教育的アセスメントに興味をもち、研究を行いました。研究を進める中で、子供を援助するためには、まずは援助者である教員が、自分自身の強みを確認することが重要であることに気づき、自分の興味や価値観を振り返るなどの自己分析や、大学教授の方々や院生の仲間達からのフィードバッグを受けることで、自分の性格や能力について深く見つめ直すことができました。
自分の強みを見つけ、築いていくことは、教師としてのキャリアの中で重要な一歩だと思います。
是非、大学院でその一歩を踏み出してみませんか。
教職大学院でしかできない学び
私は、本大学の小学校教育コースに在学していました。教職の専門性と実践力を備えた教員になりたいと考え、大学院進学を決意しました。
大学院では、コースごとに専門性を高めることのできるカリキュラムが組まれており、講義や学校教育実践実習などを通して学びを深めることができます。また、ストレートマスター・現職教員学生の院生同士の対話や、研究者の先生方・実務家の先生方に学術的な理論を教えていただきながら共に学ぶことができることも魅力だと思います。実際、私は大学院の学びを通して、「技術的熟達者」から「省察的実践者」を目指したいと、教育観や授業観を問い直すこともできました。
また、教職の専門性と実践力を高めるとともに、自分が研究したいことにじっくりと向き合う環境が整っていることも本大学院の魅力だと考えます。
校種や教科、世代を超えた仲間とともに学び、「つながり」と「専門性」を高めることができます。ぜひ、長崎大学大学院教育学研究科で新たな一歩を踏み出してみてください。
松田 大輔 先生
(教科授業実践コース[3年プログラム]令和6年度修了生、現 私立高等学校教員)
私は、3年プログラムという形で高等学校の地理歴史科の免許を取得しながら、教科指導の専門性を高めるために教育学研究科に進学してきました。
3年間という時間を大学院で過ごす中で、これまでイメージしてきた理想の授業の形を、より具体的に落とし込むことができるようになってきています。また、現職や管理職の先生方との出会いや他教科・他校種の仲間との交流を通じて、多面的・多角的な見方・考え方が身につき、私自身の教育観を深化することができました。
今年度は、高等学校の社会科教育についての研究を行い、それをもとに授業づくりと授業実践にもチャレンジしていきたいと考えています。その中で、生徒の思考がスムーズに流れることができる授業を現場でも実践できるような教員を目指していきます。
本研究科では、様々な実践を行う環境が整っており、自分のやりたいことに全力で取り組むことができます。ぜひ、「教科指導力を上げたい!」などの目的をもって本研究科への進学を目指してみてはどうでしょうか。
畑中 清二 先生
(管理職養成コース[1年プログラム]令和5年度修了生、現 公立特別支援学校教頭)
教育現場を少しの期間離れ、外側から見たり違う角度から見たりすることは、今の時代に必要な余白を生み出すことにつながる。1年間の学びは新たな教員人生のスタートとなったことを現場に戻って実感している。
講義で学んだ特定の物事や事象・人物を否定的な観点でみる「クリティカル」な視点は、自身の凝り固まった考え方や従来のやり方だけで物事を見るのではなく、様々な角度から見ることでより良い解決方法につながるヒントになり、昨今の課題である教職員の働き方にも生かせるのではないかと感じた。
ミドル層を生かした管理職と教職員に働きかけるミドルアップダウンマネジメントは組織を活性化し、課題解決力を高めることになる。これからの学校運営には必要となっていくことを学んだ。
大学院の講義は、これまで実践してきた指導法等の確認や振り返り、新たな知識の吸収の場として有意義な時間であり、小学校や中学校、高校や特別支援学校の現役の先生方との交流を重ねることで、教育の視野を広げる絶好の機会であった。
長い教員生活の中のわずかな1年間、されど深く意味ある1年間。ぜひ、このような学びの機会を手に入れるために大学院への一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。